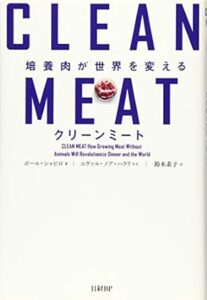
培養肉について興味があったので、この本を読むことにしました。
全体を通じて流れているのは「苦しむ動物を救いたい」という、著者や研究者、スタートアップ企業の人々の思いと熱意。
私自身も動物好きなので、本書に貫かれている「動物福祉のために果たすべき細胞農業の未来と希望」のマインドは非常に納得のいくものでした。
美味しい肉や乳製品を食べたり飲んだりする日々の中、その背景には多くの動物の死や苦しみが重なっているということ・・・
たとえそれを全て取り除くのが現状では無理でも、科学の力で少しでも改善し、いずれは全ての畜産動物を苦しみから解放したいという関係者の思い。
今回は著書の中で気に入った箇所をピックアップし(少し手直しして)、そこで簡単な自分の感想を添えていく形にしていきたいと思います。
*本サイトの記事内に広告が含まれる場合があります
培養肉について

いま私たちが立ち会っているのは、次なる食の革命の幕開けなのかもしれない。
そんな期待をかき立てるのが、細胞農業だ。
細胞農業とは、動物には手を触れず、広大な農地をより自然な生息地として動物たちに返しつつ、本物の肉をはじめとしたさまざまな畜産品を研究室で生産する手段だ
序盤の記述です。
動物には手を触れずに作り出す「食肉」。
いったいどんなものになるのか、そしてそれがどのような過程を経て開発されていったのでしょうか?(以下にまとめます)
・学問と医学の分野で開発された技術を利用して、ほんの少量採取した動物の筋細胞から生体外で筋組織をつくる
・複数のスタートアップが、この技術によって商品の開発を進めている
・動物の幹細胞に完全に見切りをつけて、牛乳、鶏卵、レザー、ゼラチンを分子レベルから生産しているスタートアップもある
・これらの製品はどれも、これまでの畜産品と実質的に同じで本物。ただし、生産過程には、まったく動物が使われていない
具体的に進められている細胞農業の分野です。
本ではそれぞれの分野をパートごとに述べる形になっています。
ただここで根本的な疑問が生じるかと思います。
「食肉のどこが具体的にだめなの?動物がかわいそうというだけの理由で?」
もちろん個人的にそれが一番ですが(可哀そうという理由)、環境に与える負荷という面も無視できません。
本書では、以下にそれらの理由が挙げられていました。
・食肉生産には、膨大な量の土地、水、肥料、石油などの資源が使われている
・食肉用の畜産動物の飼育にかかる最大のコストは飼料代だ。動物は大量の飼料を必要とする。大豆というと思い浮かぶのは豆腐や豆乳だが、世界で生産されている大豆の大半は、じつは動物の飼料になっている
・大豆の栽培には、広大な土地が必要だ。動物用飼料は熱帯雨林の森林伐採の最大の原因となっている
・世界の食肉需要の増加にともなう大豆畑の面積拡大によって、中南米の森林が破壊され、貴重な生態系が失われている
・こうなると熱帯雨林を守ろうというスローガンは、食べる肉の量を減らそう、にしたほうがより効果的かもしれない
「動物が可哀そう」だけでは済まされない被害を環境に与えていたということ。
もちろんそれは動物が好き好んで行ったわけでなく、人間が人間の都合で勝手に仕組みを作ってきた結果でもあります。
いわば「自業自得」ですね。
こうしたことに憂慮を感じている企業家は多く、グーグル創業者の一人、サーゲイ・ブリン氏も培養肉のスタートアップ企業「モサ・ミート」に投資を行っています。
・オランダの研究者マーク・ポストとピーターフェアストアラーがグーグル創業者のサーゲイ・ブリンから資金提供を受け、2013年に培養肉ハンバーグを発表し、2016年には培養肉の特許関連会社モサ・ミートを創業した

ただいくら「食用の牛を育てるのがよくない」といっても、肉好きな人には聞き入れてもらえません。
動物への憐憫の想いは人によって感じるところが違いますし、環境への負荷も当事者がそれによって悪影響を受けているという実害がなければ、なかなか実感として湧きにくいものでもあります。
なによりも「味」が一番の問題でもありますよね。

そのために開発者は味の研鑽にも尽力している模様。
モサミートの創業者の一人、マーク・ポスト氏も次の言葉で期待を寄せています。
「味が従来の肉と同じか、それ以上であれば、消費者はクリーンミートを選ぶはずだと信じている」
クリーンミートにはもう一つメリットがある。肉をとるために動物を苦しめたり、殺さなくてもいい点だ。昔ながらの肉を食べつつも、その肉がお皿の上に乗るまでにどんな風に生き、死んだかについて心配していない人は多い。サーゲイ・ブリン(グーグルの創業者)が培養肉に興味をもったのも、それが理由の一つだからだ。「肉牛がどう扱わているかを知ったら、どうしたって落ち着いていられなくなるからね」
培養レザーについて

食肉同じく、多くの皮革製品にも動物の体の一部が使われています。
培養肉の一般的な流通には、それを可能にするための開発も重要ですが、それと同じくらいに「消費者に受け入れられること」も大切です。
とくに食肉は口に入れるものなので、培養肉という「人工の肉」に心理的抵抗を持ってしまうのは仕方のないことです。
なのでまずは「培養肉」そのものを認知してもらうという意味で、レザーを買ってもらおうという動きもあるということ。
それが人工的に作られた「培養肉」を使った「培養レザー」です。
・培養レザーは初期培養ビジネスの出発点ともいうべき製品
・クリーンミート(培養肉)は素晴らしい製品だが、口にいれるのに抵抗がある人が多い可能性がある。服飾やファッションとしてのレザーであれば、食べる培養肉よりも人々に受け入れられる素地がある。食べる前に”身につける”ことで、消費者もアニマルフリーの培養農産品を使うというコンセプトに馴染む
こうした考えのもとに創業されたのが「モダン・メドウ」です。

アメリカのスタートアップ企業で、細胞から作り出した牛肉やレザーで皮革製品を開発・販売しています。
培養肉の認知を広める「先兵」としての役割を担う培養レザーですが、注目すべき働きはそれだけではありません。
レザー製品を作る時に生まれる「有害物質」を防ぐ意味もあるのです。
以下はそのあたりの情報(記述)をまとめたものになります。
・アメリカの皮革業界は世界的な巨大産業。輸出だけとっても年間30億ドルの牛革を輸出している。解体された牛3500万頭分にあたる分量だ。アメリカ国内では、牛革の約2分の1は靴に、3分の1は家具やカーシートに、残りはアクセサリーに使われている。それに加えて牛の皮がレザーになる過程で別の問題も生じている。たとえば腕時計の皮ベルトが腐らないように「なめす」作業を伴うということ。動物の皮をミイラ化するための工程で、この中でさまざまな化学物質が使われている
・皮なめしの工程では、皮に残った毛や脂肪などを強アルカリ性の石灰液を用いて、化学的に取り除く。取り除かれた部分は化学薬品ともども廃棄される。次に皮をクロム液す工程もある。クロム液は腐食性の物質で、そのまま下水に流されることがある
・皮なめしの大国といわれるインドやバングラディッシュのような環境規制の緩い国では、硫酸クロムや硫酸など、皮なめしに使われる有毒な化学物質が日々、排水処理もされずに自治体の下水道に垂れ流されている
・インドの皮革産業の中心地カーンプルでは、皮革工場の廃水によるガンジス川の汚染があまりに進んだため、政府は2009年に一体の皮なめし工場の4分の1以上にあたる汚染源のうち最悪の100か所以上を閉鎖せざるを得なくなった。汚染水は地域住民の皮膚炎、呼吸器系疾患、腎不全などの発生率の上昇と高い相関を示している
・特に水生の生物は、とりわけ大きな被害を受けている可能性がある。皮なめし工場付近の水路はデッドゾーンとなり、その名の通りに生き物が生息できない場所となる
・これらの現状を知っていれば、皮を動物からとるのではなく、研究室で培養することに価値があるのは明らか。モダンメドウで作るレザーには、毛も肉も脂肪分もないため、皮なめしの工程や時間、手間をかなりの部分を短縮できる。必要な作業は保存処理と用途に応じた厚みの調整、つまり通常の皮なめしの最終段階だけで済む。だけだ。化学物質を使わないため、政府が定めた皮なめしの工程における化学物質の廃棄規制を心配する必要もない
上記の状況は本書が出版された2020年以前のことと思われるので、現在はまた状況が異なっているかもしれません。
これはたまたまインドであったことで、他の国でも同様のことが起こる可能性もあります。
となると、場所に関わらず「皮をなめす工程に改善が必要」ということ。
そして培養レザーを使うことで、大きく解決できる可能性があるということ。
培養肉と同様に、多くの動物の命と人々の健康、地球環境を守ることができるということで希望が持てます。
日本のスタートアップ企業も培養レザーや関連商品で取り上げられており、国内での細胞農業の息吹と活力の芽生えを感じます。
・日本の競合企業の「スパイバー」は、別のアウトドアブランド「ザ・ノースフェイス」との共同開発により、2015年に耐久性に優れたスパイダーシルク入りの防寒ジャケット「ムーン・パーカ」を発売している
・運動靴メーカーのアディダスも、スパイバーと競合するドイツのバイオ企業アムシルクが開発した培養スパイダーシルク「バイオスティール」製品化している
鶏卵・鶏肉の培養について
細胞農業の活躍する分野は牛肉だけではありません。
牛と同様に世界中で多く家畜として飼われている「鶏」もその対象です。

本書では、鶏は牛以上に悲惨な状況に置かれていると書かれています。
その理由は様々ありますが、個人的には大きく分けて「個体が小さく飼育するのに場所をとらないこと」「卵を産むこと」にあると考えます。
それについて説明した記述を以下に順を追ってまとめていきます。
・ジョシュ・テトリックとジョシュ・バルクによって2011年に設立された「ハンプトン・クリーク」(現在はジャストに社名の変更)は、鶏卵不使用の鶏卵製品(マヨネーズ、クッキー生地、スクランブルエッグなど)を開発。現在は家禽類のクリーンミート開発も手掛けている
・畜産動物の福祉の観点から厳密にみれば、畜産業による苦しみの圧倒的多数を担っているのは牛ではなく、鶏。
・アメリカの畜産動物のほとんどは家禽類で、年間3500万頭の牛が食肉に解体されるのに対し、殺される鶏の数は90億羽にのぼる
・牛は生まれてしばらくは牧場で過ごすうえ、肥育にはいったあとも戸外を歩き回ることはできるが、食肉用の鶏や七面鳥、鴨といった家禽類は通常、窓のない倉庫の中に何万羽も一緒に、死ぬまで閉じ込められる
・バタリーゲージと呼ばれる「鶏が羽を広げることもできない狭さ」の場所の中で、鶏は一年以上動けないまま、次々に卵を産むように強いられている
・動物愛護活動家が何十年も前から養鶏業界に改善を求めているが一向に進まない。その理由は「ゲージ飼育をやめるとコストがかさむ」ということ
・通常よりもずっと早く解体に回せられるよう、体重を急速に、そして不自然に増加させるための遺伝子操作をされているため、多くは慢性的な痛みを抱えている
・クリーンな代替肉に置き換えるとしたら、牛肉よりも家禽類の肉を選ぶ方が、苦しむ動物の数をはるかに減らせる
・鶏卵を多く使う食品会社にとって、クッキーもケーキもパンも、卵を使わずに同じものを安く作れることは分かっている。豆などの植物性タンパク質は鶏卵よりも安価
上記に書かれている鶏が置かれた「悲惨な環境」を改善するために、ハンプトン・クリークのようなスタートアップが培養肉の技術を鶏肉に活かしたり、鶏卵の培養製造に力を入れているということになります。

個人的には、鶏がここまで悲惨な環境で飼育されていることが初めて知りました。
飼育ゲージの問題は日本でも時々メディアで取り上げられてきましたが、肉の消費量が日本よりはるかに多いアメリカでは、より規模が拡大された形で常態化しているということなんでしょうね。
動物愛護の精神が多くの国でも認知され始めていると思いますが、現状はまだまだこれからというところなのかもしれません。
その意味で鶏の培養肉や人口鶏卵は道徳心に頼るよりも、より確実に事態の悪化を抑えられるとも思いますね。
もちろんすぐに環境を変えることは困難ですので、培養肉が広く進むまでは、人間の意識的な変化も必要なのは確か。
その意味で以下の記述は確かにそのとおりだなと感じました(クリーンミートのスタートアップに投資するストレイドッグ・キャピタルのCEO、リサ・フェリア氏の言葉です)
”殺される動物の数や苦しみを減らしたいと願い、それでも動物の肉が食べたいのであれば、鶏肉から牛肉に切り替えることです。鶏肉より牛肉の方が、1食分あたりの苦しみはずっと少なくて済みます。牛1頭からとれる肉の量は鶏一羽からとれる肉より、何百食分も多いうえ、生前の牛は鶏よりもずっとましな扱いを受けているからです。もちろん、鶏も牛も食べなくて済むなら、それに越したことはありませんが”
喩えが極端で汚いですが「世の中はほとんど糞みたいなもの」という発想をベースにした考え方で「同じ糞なら少しでもマシな糞を選べ」がまさにそれに当てはまりますね。
細胞農業による乳製品・液卵白の生産について

牛肉、鶏肉、鶏卵に続いて「乳製品と液卵白」について書かれています。
乳製品は牛の乳になるので「どうやって代用するの?」と思いましたが、これも細胞農業の技術で再生が可能だというのです。
この辺りの記述は専門風のものになるので、正直理解が難しかったのですが(というか、全ての分野でですが苦笑)、詳しくは本の内容で確認してもらえればと思います。
以下にそれを実現した企業と、乳牛を代用する意味と目的についてまとめますね。
・2014年に設立したスタートアップ企業「パーフェクトデイ」が、酵母を使った人工牛乳を開発

・多くの人は乳製品の消費についてほとんど考えない。牛がたまたま乳を出しているのだから、人間がそれを消費するのは自然なことだと思っている。
・現実派、あらゆる哺乳類と同じように、牛も妊娠すると乳を出し、そしてその乳は人間ではなく子牛向けにできている。酪農家は牛乳が出続けるよう、人口受精で牛を常に妊娠させておき、乳を搾る。牛乳を売るために、生まれた子牛はその日のうちに母牛から引き離される。子牛は思春期になると使用済みの母牛の代わりに乳牛の列に加わるか、子牛肉あるいは牛肉にするために飼育される
・現代の乳牛は、品種改良を重ねて先祖の何倍もの乳を出している。酪農業界における恒常的なホルモンや抗生物質の投与がこの事態に拍車をかけ、牛たちは、さらに多くの乳を出すよう強いられている。分泌する乳量が多すぎることが原因で、牛の歩行困難や乳腺炎など、動物福祉にかかわるさまざまな問題も増加している
私もミルクは「牛が自然に出したもの、または余ったもの」という認識でした。
本書で書かれたアメリカの乳牛の飼育法やミルクの絞り出し方については「ひどい」の一言に尽きます。
もちろんそれを飲んでいる自分もあり、牛肉が美味しいという自分という事実もあるので、偽善的なのは重々承知ですが、それにしても・・・という思いです。
本書が書かれた当時の情報ですし、日本ではアメリカとは異なる方法で搾乳しているかもしれません。
これが今でも行われていて事実だとすれば、こうしたことを防ぎたい一心で「人口ミルク」を作ったスタートアップの創業者の熱い思いは評価すべきだと感じます。
日本でもこのミルクが飲める日がくると良いですね。
そしてもう一つが「液卵白」です。
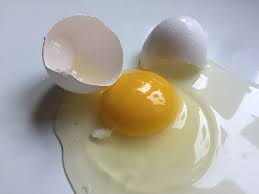
恥ずかしながら初めて知った食材です。
これも卵から作られるようで、それを生む液卵白用の鶏もいるのだとか。
そしてその鶏の飼育がより悲惨だというのです。
「液卵白など加工卵用の採卵鶏は多くの場合、畜産動物のなかでも最悪の扱いを受けている。パック入りでスーパーに並んでいる殻付き卵用の採卵鶏は通常、ゲージにびっしり詰め込まれて飼育されている」
う~むという感じですよね。
普通の卵を産む鶏の扱いだけでもひどいのに、液卵白用の卵を産む鶏がより最悪な状況下にいるとは・・(このあたりの実態の詳細は本で確認してみてください)
これを防ぐために登場したのが、細胞農業による液卵白の生産を目的とするスタートアップ企業「クララフーズ」です(現在は社名を「The every company」に変更)

「天然の卵白をもってきて、卵白を構成するタンパク質を分離し、それを再合成して、天然の卵白と同じように調理でき、同じ味がする卵白を作る」
という生産法を実施し、見事に成功したということ。
先ほどの液卵白用の鶏の環境を考えると、一日でも早く、この培養による液卵白の普及が広まることを願いたいですね。
まとめ
以上ざっとですが、本書で気になるポイントと記述、それに関する補足と感想をそれぞれまとめさせてもらいました。
培養肉に関する一般的な情報と自分の思いは、以前に書いた別記事でも説明していますが、改めて本書を読んで感じたのが「少しでも多くの動物の苦しみを軽減してあげたい」ということ。
肉が大好きで普段もよく食べている自分的にも、培養肉が実用化されたとすれば、罪悪感を感じずに食べられることになるのかと想像します。
本書でも述べられていましたが、人間は肉が本当に好きな動物。
古来から豊かになれば「肉」を祝いとして食べてきた歴史がありますし、いまでも御馳走といえば「肉料理」が食卓に並べられる家も多いかと思います。
そんな肉への本能的な欲求と喜びをもつ人間に「肉を食べるな」というのは、あまりにも酷というものですし、おそらく止めるのは無理でしょう。
でも培養肉であれば「肉を食べる」欲求を満足させることができますし、同時に動物の犠牲をなくすことも可能。
もちろん実現には様々なハードルがあります。
培養肉企業サイドの製品化のための生産技術の向上や味の改善はもちろん、肉の生産で生計を潤してきた畜産家や農家の経済的な問題、食肉業界との確執、そしてもっとも大きいのが「消費者が培養肉を受け入れるのか」という意識の問題・・・
課題山積という感じですが、環境保護や食料不足を解決するための手段として、いずれ来る宇宙時代の食料確保、そして何よりも「人と同じく命ある動物たちを守るため」として、ぜひ実現して欲しいと心から願っています。
関連まとめ

