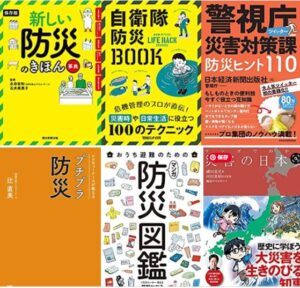
防災に関する書籍の紹介です。
万が一の災害や、あってはならない不測の事態に対応するための内容を取り扱っています。
自分が持っているものや、これは買おうかなと考えている防災本、読みやすい漫画本をそれぞれ5つ、合計10冊を紹介していきます。
*本サイトの記事内に広告が含まれる場合があります
おすすめ防災本【5選】
まずは書籍版です。
防災全般の知識から、医療の専門家による視点、防衛産業のプロや組織が伝える防災知識が身につきます。
いざというときのために知っておいて損はないラインナップをチョイスしています。
新しい防災のきほん事典
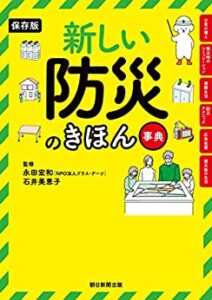
防災についての情報とテクニックが豊富なイラストでまとめられた防災本です。
とにかく読者フレンドリーな内容で、文字の配列とイラストや図表の配置が絶妙で「読みやすい」。
大判でページ数も多いわりに「軽い」です。
内容が充実していて軽いので、防災リュックに入れても嵩張らないのが助かります。
この一冊さえあれば、おおよその防災情報はカバーできると思います。
プチプラ防災

国際災害レスキューナースさんによる書籍です。
看護のプロならではの医学知識を生かした防災法が充実していて、他の防災本にはない合理的な手法で身を守る術を教えてくれています。
ペットや赤ちゃん、高齢者の避難法にもきちんと対応策を述べていて、災害弱者への目配りも忘れない看護師さんならではの冷静な意見は非常に参考になりました。
自衛隊防災BOOK
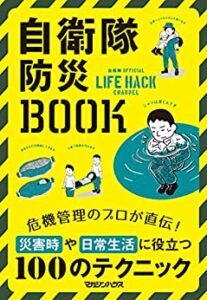
サバイバルのプロである自衛隊監修の防災対策本です。
いざという時の人命救助や水・食料の確保などを写真付きで優しく解説してくれています。
続編も出版されており、初版に比べてより普段使いに向いた内容になっています(⇒自衛隊防災BOOK 2)
警視庁災害対策課ツイッター 防災ヒント110
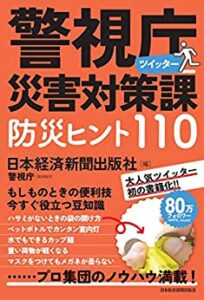
ツイッター上でアップされた防災術を一冊の本にまとめた書籍です。
「日常の防災術」を中心に情報がまとめられています。
手軽に使える「かんたん防災」な内容が魅力で、普段使いの防災術としておすすめの書籍です。
民間防衛~スイス政府編
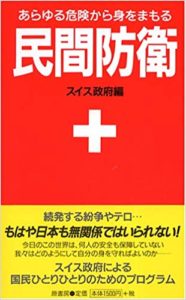
スイス政府が刊行した家庭用防災ハンドブックの日本語版で、20年ほど前に初めて日本で和訳本が紹介されて話題を呼んで以来、長く支持を受けている防災本の一つです。
スイスは平和なイメージがありますが、実は国民皆兵(徴兵制)の歴史が長く(800年代~)、今でも国民の義務として兵役を担うシステムが続いています。
非常時の組織づくり(避難所の管理や自警団への応用)や救護・消火活動など、一般的な防災対策法としても使える部分がかなりあり、防災の教養書としておすすめです。
おすすめ防災マンガ本【5選】
防災全般の知識や歴史に絡めた体験談、自宅避難する際のコツやポイントなど、色々な立場の人がそれぞれの視点と経験でまとめたマンガ本です。
文字情報よりも状況がイメージしやすいので、スッと頭に入ってきやすいのが魅力ですね。
大人からお子さんまで幅広い防災を学べる「マンガ書籍」を紹介していきましょう。
マンガ防災図鑑
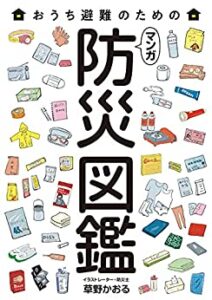
防災に関する基礎知識をバランスよく網羅しているマンガ本です。
イラスト風のマンガも癖がなく、読みやすくなっています。
実践的な内容になっているのも特徴で、状況ごとの対応策がまとめられている点もポイント。
広く多くの人におすすめしたい防災マンガ本ですね。
マンガでわかる災害の日本史
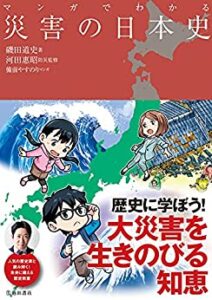
歴史学者の磯田道史さんが監修した災害歴史マンガです。
災害大国である日本の災害史を学ぶことで、未来の災害に対する備えをしていく氏の学問姿勢にはすごく共感できます。
実際に起きた災害から学ぶ以上に「実践的」な防災はないですからね。
マンガも丁寧に描かれていて読みやすいですよ。
避難所に行かない防災の教科書
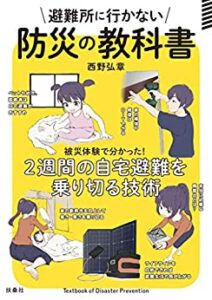
2019年に起きた台風で自宅のライフラインが断絶した経験をマンガにした実践本です。
自宅を自分で作り上げた著者による、超実践的な「在宅避難の方法」が網羅されています。
家を知り尽くした人だからこそ伝えられるリアルな防災術や、一般の人でも使える基礎的なものまで幅広い内容が魅力。
マンガもアニメ風のイラストと写真が組み合わされていて、とても読みやすいですよ。
サイエンスコナン・防災の不思議
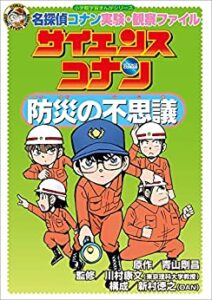
名探偵コナンのキャラクターで防災の大切を伝えるマンガ本です。
災害が起きる仕組みを科学的に説明しつつ、現場の対応策を分かりやすく説明しています。
コナンのマンガで描かれているので、文字だけの情報だと敬遠してしまうような内容がスッと頭に入って来るのが魅力ですね。
お子さんにおすすめしたい防災への取り組みガイドですね。
クレヨンしんちゃんの防災コミック
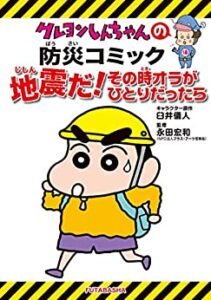
人気漫画のクレヨンしんちゃんによる防災ガイド本です。
親しみやすいマンガのキャラクターを使っているので、子供には難しい防災の知識が伝えやすい内容になっています。
あくまで防災の基礎知識ですが、知っているとの知らないのでは助かる確率が大きく違ってきます。
子供にも分かりやすい内容になっているので、お子さんがいるご家庭にはぜひおすすめしたいですね。
まとめ
これまで買ってきた本、欲しい防災本のリストを挙げてみました。
防災の知識はSNSや動画でも学べますが、本(電子書籍)という形でまとまった文字情報から学べるものも多いと思います。
長い文字情報が苦手な方はマンガもおすすめですし、お子さんにはそちらのほうが良いかも知れません。
それぞれのご家庭に合う方法で、ぜひ参考にしてくださいね。
関連まとめ















